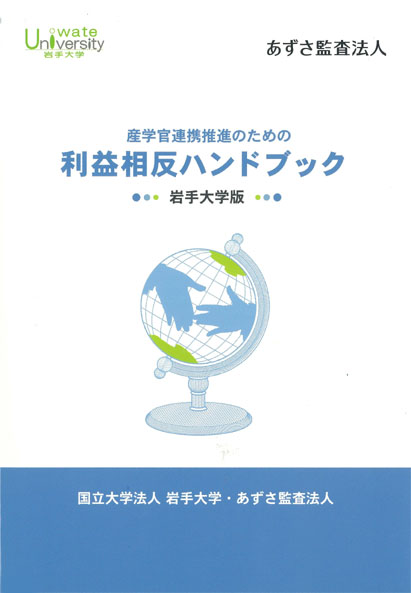− 産学官連携のノウハウ −
おかげさまで、完売致しました。
改訂版の出版は、現在検討中です。
| 利益相反ハンドブックの刊行にあたって 2004年4月1日、岩手大学は、国立大学法人岩手大学が設置する大学に移行しました。この制度上の大きな変化は、新制大学発足以来の大きな出来事であり、各大学はこれまでの画一的な運営体制から脱皮し、個性を鮮明にした自立的な活動を展開することが求められています。 岩手大学は、「学生の立場に立った教育サービスの充実」、「地域特性を踏まえた研究の重視」と共に、「地域連携強化による教育研究成果の社会還元」を活動の大きな目標に掲げています。特に、平成15年度文部科学省の大学知的財産本部整備事業に採択されたことを受け、大学の研究成果の技術移転による地域産業の活性化や新産業の育成を図るとともに、大学に還元された資金で新たな研究の進展を促す「知的創造サイクル」の確立を目指しております。また、工学部、農学部を中心とした科学技術の分野ばかりでなく、生涯学習、文化、知性などの様々な分野に関わる知的財産をも活用すべく、経済界、行政、住民の方々と手を携えた新たな連携の体制を構築したいと考えています。 しかし、大学の構成員が具体的な社会貢献を推進する場合に、本来の職務である教育、学術研究とのバランスが崩れ、大学としての社会的責務を全うし得なくなったり、連携を進める産学官の各個人や組織同士が互いに相容れない課題に直面する事態が起こりかねません。すなわち、大学または大学の教職員が連携活動に伴って得る利益と教育や学術研究という大学における責任が衝突・相反している状態(狭義の利益相反)や、教職員の大学における職務遂行の責任と兼業をしている企業などに対する遂行責任が両立し得ない状態(責務相反)などが現実の問題となっています。 これら「利益相反」は、大学が社会に対して果たすべき役割を推進していく中で必然的に生じてくるものです。それ故、私たちは、「利益相反」に対する適切なマネジメント体制を整備すると共に、その理解度を深めて自らを律することが求められます。 本ハンドブックは、岩手大学知的財産ワーキンググループと利益相ワーキンググループの検討結果に基づき、あずさ監査法人様の多大なるなるご協力のもとで制作されたもので、私たちに、これまであまり意識してこなかった「利益相反」に関して、わかりやすく解説し、また具体的な事例を紹介したものです。今後の産学官連携、社会貢献を進める上で、身近な手引き書として活用くださるようお願い申し上げる次第 です。 2004年4月
|