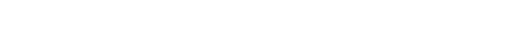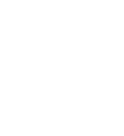R7.07.26 公開講座「環境学入門」~人文社会科学部地域政策課程・地域環境プログラムの紹介~ を開催いたしました
令和7年7月26日(土)に公開講座「環境学入門」~人文社会科学部地域政策課程・地域環境プログラムの紹介~ を開催し、8名の方にご参加いただきました。
岩手大学人文社会科学部地域政策課程 地域環境プログラムでは、環境の視点から持続可能な社会づくりの諸課題に取り組み、地域社会に貢献できる人材の養成を目的として教育研究を行っています。
本講座は、高校生を主対象として、「環境学」を焦点とするプログラムの教育研究の内容を紹介するとともに、地域社会に関わる課題について、環境リスク学・環境生態学・環境社会学・環境経済論・環境政策論の各分野から話題を提供する講座です。
今回は5つの講義が行われ、環境共生プログラム研究室担当教員が講師として各分野の研究内容を紹介しました。
講座1:寺崎正紀(環境リスク学・教授)「東北のプラスチックごみの問題と化学物質の政策を考える」
東北におけるプラスチックごみの問題に加え、⽇常的に使っている製品からも汚染が広がっている現状を説明し、こうした環境問題がどんなリスクをもたらすのか、地域ではどんな対策ができるのかについて紹介しました。
講座2:金森由妃(環境生態学・准教授)「気候変動が生物に与える影響」
気候変動による環境の変化は、生物にどのような影響を与えているのか、今回は主に海洋生物の研究事例を紹介しました。
講座3:塚本善弘(環境社会学・教授)「日本・岩手の住宅は何故、寒い?-背景と対策の進展-」
これまで岩⼿や国内の多くの住宅が寒かった背景を、文化・社会的要因や法制度的側⾯から考察するとともに、岩⼿を含め⼀部⾃治体で進展し始めている対策(政策展開)についても紹介しました。
講座4:朴香丹(環境経済論・准教授)「環境問題への経済学の観点からのアプローチ」
経済発展によって環境問題が引き起こされた背景から、環境保全と経済発展を両立した持続可能な社会を実現するための研究を紹介しました。
講座5:中島清隆(環境政策論・准教授)「持続可能な地域社会形成に向けた3つの連鎖的な市民共同太陽光発電所の再生可能エネルギー普及方策」
東⽇本⼤震災の復興から「新⽣」とも表現できる持続可能な地域社会の形成を⽬指して、岩⼿県内被災地コミュニティでの市民共同太陽光発電所の建設・運営に、被災地外における2つの市民共同太陽光発電所が関わることで連鎖していった再⽣可能エネルギー普及方策の⼀例について紹介しました。
参加されたみなさんは、講義に熱心に耳を傾けていました。学びへの意欲を高めるきっかけとなれば幸いです。