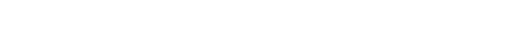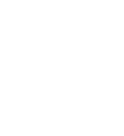R5.7.1 公開講座 『第27回農学部5学科 「植物生命科学科」「応用生物化学科」「森林科学科」 「食料生産環境学科」「動物科学科」の実験講座』を開催いたしました
- 目的
本講座は、主として岩手県内の高校生や理科教育に携わる教員の方々を対象とする、実験やフィールドワークを中心とした公開講座である。講座では、5つの学科で活躍している教員を講師として、現在進めている研究や実験の様子をわかりやすく説明し、教科書では得られない「科学の面白さ」を体験してもらうものである。
- 活動実績
コース1:植物のウイルス病を診断してみよう(植物生命科学科 磯貝雅道 教授)【5名】 植物ウイルスの形態観察および抗原抗体反応によるウイルス病診断のため、電子顕微鏡およびImmunoStripを用いた実験を行った。実験の前に、植物ウイルス病診断の重要性について講義を行い、各実験の意味・意義について、高校生でも理解できるように工夫した。
コース2:花、野菜、および果物の色とアントシアニン(植物生命科学科 立澤文見 教授)【6名】 園芸作物(花、野菜、果樹)約20品目から、見た目の色とアントシアニンの関係を調べてみたいものを各自5つずつ選び、分析実験をした。実験の待ち時間で講義を行った。そして、教科書に書かれている植物の色に関する内容は一部間違っていることを理解してもらった。
コース3: DNAと遺伝子検査について学ぼう(応用生物化学科 斎藤靖史 准教授)【7名】
口腔内の細胞からDNAを抽出し、PCRにより気分に関わるとされるセロトニントランスポーター(HTT)の遺伝子断片の増幅を行った。電気泳動によるサイズ測定を行い、短い不安型HTT、長い楽観型HTTどちらの遺伝子型をもっているかを鑑定した。DNA、遺伝子解析手法を実際に体験し、DNA多型と遺伝子検査、ゲノム情報の重要性について学習して頂いた。
コース4:土は生きている?-土壌微生物と土壌動物の役割(応用生物化学科 立石貴浩 准教授)【8名】
大学構内の林で、落ち葉の分解の様子や土壌の特徴を観察した。実験室では、土壌の基礎に関する講義を行った。次に、簡易ツルグレン法により森林の落ち葉の試料から採取した土壌動物の観察、各種土壌の呼吸量の測定、吸着能の評価、草本植物の根に感染したアーバスキュラー菌根菌の観察を行い、土壌中に多様な生物が存在することを確認してもらった。
コース5:木の香りが持つ不思議なチカラ(森林科学科 小藤田久義 教授)【4名】 樹木の香り成分(精油)が持つ機能についての概説と当研究室の研究紹介を行ったのちに、水蒸気蒸留法によるスギ木材からの精油の分離を行った。あわせてガスクロマトグラフィーおよび薄層クロマトグラフィーによる分析方法について説明し、スギ材精油を用いた成分分析の実験を行った。
コース6:水路の流れをコントロールする(食料生産環境学科 飯田俊彰 教授)【6名】 広域にひろがる農地へ灌漑用水を届ける仕組みと水路での水流のコントロールの必要性について説明した後、実験水路で量水堰の流れと跳水現象を観察した。実際に跳水の前後の水深を流下方向に20cm間隔で測定し、跳水前後の水面形を把握した。最後に、パソコン上で不等流の水面形解析ソフトを用いて、実測値が計算値によって再現できることを体験してもらった。
コース7:堆肥化を科学的に理解する〜有機物分解の評価〜(食料生産環境学科 前田武己 准教授)【5名】 農業から発生する廃棄物では家畜排せつ物が多く、その多くは資源化されて農地に施用されること、その資源化技術は堆肥化が中心であることなどについて、スライドを用いて説明した。その後実験室に移動して、気浴保温式の堆肥化実験装置の概要と実験手順の説明を行い、実験の中の材料温度と排気酸素の測定値の説明を行った。
コース8:動物からの贈り物を科学する-動物の筋肉を比べてみよう、牛乳をチーズに変えてみよう (動物科学科 村元隆行 准教授)【8名】 動物の種類によって筋肉の色が違うのはミオグロビンの含量の違いであることを説明し、測定器を使って筋肉の色を客観的な数値として表す方法を学ばせた。また、牛乳に含まれるカゼインを酸で凝固させることによってチーズが製造できることを説明し、2種類の酸を使ってチーズの製造を学生と行った。