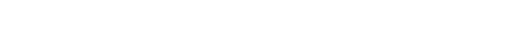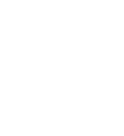R5.10.7 公開講座「環境学入門」を開催いたしました。
令和5年10月7日(土)に公開講座「環境学入門」を岩手大学教育学部北桐ホールで開講いたしました。
・目的
岩手大学人文社会科学部地域政策課程環境共生プログラムでは、環境の視点から持続可能な社会づくりの諸課題に取り組み、地域社会に貢献できる人材の養成を目的として教育研究を行っている。今回の公開講座では、高校生を対象として、「環境学」を焦点とする本プログラムの教育研究の内容を紹介するとともに、地域社会に関わる課題について、環境リスク学・環境社会学・環境政策論・環境経済論の各分野から話題を提供し、その結果、環境共生プログラムに興味を持って頂き、同プログラムの受験生を増加させることを目的といたしました。
・活動実績
全体の司会と総合討論を地域政策課程環境共生プログラムの竹原明秀(環境生態学・教授)が担当した。
第一講義「忍び寄るプラごみ問題」を寺崎正紀(環境リスク学・教授)が担当し、現代社会に広く普及しているプラスチックが、海洋での大きな問題(プラごみ)を生じさせている状況を東北地方沿岸や北上川での研究事例を紹介し、身近な環境問題をわかりやすく解説した。
続いて、第二講義「旧松尾鉱山による公害・北上川汚染と現在のリスク」を塚本善弘(環境社会学・教授)が担当し、岩手県で100年以上前からある公害として、旧松尾鉱山廃水問題を取り上げ、その歴史的経緯を振り返りながら、そこに存在する課題やリスクなどを考察した。
休憩を挟み、第三講義「持続可能な「いわて」地域社会の形成に向けて―環境政策研究(論)と持続可能な地域社会(形成)研究の観点から」を中島清隆(環境政策論・准教授)」が担当し、東日本大震災以降の持続可能な「いわて」地域社会の形成に係わる2つの取り組み事例を紹介し、その取り組みの現在までの成果を分析した結果を紹介した。
最後に、第四講義「持続可能な社会づくりに向けて―教育、環境配慮型行動と経済発展について」を朴香丹(環境経済論・准教授)が担当し、SDGs(持続可能な開発目標)が求められている現状下でも地球環境問題は深刻化しつつあるが、経済学の観点から解決する道筋があることを実証研究の結果から報告し、地球環境問題への対策について紹介した。
・今後の課題
今回、設定した開催日は学校推薦選抜試験の日程を考慮したが、10月7日は三連休の初日にあたり、様々な行事が行われていたため,申し込む受講生が少なく、日程の設定を充分に検討する必要といえる。しかし、申し込まれた受講生は全員出席し、やや高度な内容であったが、満足度は非常に高いことがアンケート結果から確認できた。以上から、公開講座を実施したことにより、高校生の将来の進路に寄与できた。