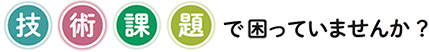教員別一覧
No.31
- 農学部
-

- 植物生命科学科

- 園芸学分野
蔬菜花卉園芸学研究室
- 准教授
- 立澤文見
- たつざわふみ
- シーズのポイント
- 新しい色の花や野菜を育種するための基礎となる色素に関する研究
- シーズ概要
-
花や野菜にはいろいろな色があります。この色に関わる色素の内、特にアントシアニンという色素による色の発色に関する基礎研究を進めています。花や野菜の色の研究では、同じ色素で違う色、違う色素で同じ色ということがよくあり、この原因を色素のレベルでしらべます。そして、応用として新しい色の花や野菜の品種改良の可能性を探ります。
- 【主な研究テーマ】
-
- アブラナ科植物の新花色花卉育種に関する研究
- 主要切花、鉢物、および、花壇用花卉作物の花の発色機構に関する研究
- 野生植物の花色分析と遺伝資源としての可能性に関する研究
- 遺伝子【主な研究テーマ組み換え体や培養変異体の花色素の同定および色素生合成系遺伝子の探索
- ラン科植物の花色とアントシアニンに関する研究
- 黒米(作物)とダイコン(蔬菜)の色素の分析
No.32
- 農学部
-

- 植物生命科学科

- 応用昆虫学分野
応用昆虫学研究室
- 教授
- 佐原健
- さはらけん
- シーズのポイント
- ゲノム創農薬に活用できる遺伝学的基盤を確立する研究
- シーズ概要
-
昆虫の持つ能力をより理解することを目差しています。それらを活かせば、昆虫機能利用が実現できます。それらを弱めれば害虫防除に応用が考えられます。また、昆虫の辿ってきた進化を分子レベルで理解する研究を行っています。
No.33
- 農学部
-

- 応用生物化学科
- 准教授
- 鈴木雄二
- すずきゆうじ
- シーズのポイント
- 光合成の能力を改良することで植物の生産性を向上
- シーズ概要
-
植物の光合成の能力を決定するメカニズムを解明するとともに、光合成の能力を改良することで植物の生産性を向上させるための研究を行っています。
No.34
- 理工学部
-

- システム創成工学科
電気電子通信コース
- 教授
- 長田洋
- おさだひろし
- シーズのポイント
- ザゼンソウという恒温植物を材料に、連合農学研究科との共同研究により、生体由来の発熱制御機構の解明と、それに基づく工学的温度制御システムの開発
- シーズ概要
-
岩手県等の寒冷地に自生する、氷点下を含む外気温度の変動にも関わらず体温を20°C程度に維持できるザゼンソウという恒温植物を材料に、連合農学研究科との共同研究により、生体由来の発熱制御機構の解明と、それに基づく工学的温度制御システムの開発に取り組んでいます。
No.36
- 農学部
-

- 植物生命科学科

- 作物学分野
作物学研究室
- 教授
- 下野裕之
- しものひろゆき
- シーズのポイント
- 異常気象に負けない作物を育てるための機構の解明、冷害、高CO2下での多収性、湿害、直播、量的遺伝子座についての研究
- シーズ概要
-
世界の食料危機の克服を目指し岩手から地球規模の課題に挑戦しています。私たち人類の生命は野外環境である農地で栽培される植物の光合成活動により支えられています。作物学研究室では、地球温暖化などにより栽培の適地が制約される中、単位土地面積当たりの作物の生産性の向上を目指しグローバルに研究を進めています。
No.38
- 農学部
-

- 応用生物化学科

- 土壌学研究室
- 准教授
- 立石貴浩
- たていしたかひろ
- シーズのポイント
- 土壌中での微生物を介した養分動態や土壌微生物の有用機能の利用
- シーズ概要
-
土壌中での微生物を介した養分動態や土壌微生物の有用機能の利用に関する研究を行っています。
アンモニアを好むキノコやカビの仲間(アンモニア菌)を利用して、家畜ふん尿を原料とした堆肥製造過程でのアンモニア揮散を防ぎ、肥効性が向上する堆肥製造システムの開発を目指しています。従来の堆肥製造法に比べて、窒素含量の高い堆肥の製造が可能になるかもしれません。
No.39
- 農学部
-

- 食料生産環境学科
食産業システム学コース 
- 農業循環科学研究室
- 准教授
- 前田武己
- まえだたけき
- シーズのポイント
- 農畜水産業における未利用資源の循環利用、廃棄物処理の効率化
- シーズ概要
-
農業を持続的に発展させるために、家畜排せつ物や作物残渣といった生物系廃棄物を有効利用する技術について研究しています。
- 【主な研究テーマ】
-
- 生物系廃棄物の堆肥化技術
- 堆肥の品質向上と効果的な利用
- 水産系を含む食品廃棄物の減容化技術
No.40
- 農学部
-

- 食料生産環境学科
農村地域デザイン学コース 
- 土壌圏循環学研究室
- 准教授
- 武藤由子
- むとうよしこ
- シーズのポイント
- 農地と寒冷地の土壌について、その物理的条件が微生物活動由来の物質動態に与える影響を研究
- シーズ概要
-
土壌の物理的性質(構造・水分特性・移動現象など)の視点から、作物の生産性の向上や環境保全を目指し、土壌中における窒素動態を明らかにするための研究を行っています。
- 【主な研究テーマ】
-
- 土壌中における水移動と窒素動態の関係
- 水田での水管理が窒素動態と水稲の生育に与える影響
- 畑地土壌の水分量と電気伝導率モニタリング
- 緑化を目的とした土壌物理性の改良
No.41
- 農学部
-

- 食料生産環境学科
食産業システム学コース 
- 農産物流通科学研究室
- 教授
- 小出章二
- こいでしょうじ
- シーズのポイント
- 農産物・食品の保蔵、穀物加工貯蔵、青果物の鮮度保持、野菜の安全な殺菌についての研究
- シーズ概要
-
生鮮農産物は生きています。生きているから、私たちは農産物に対して手荒な扱いが出来ません。でも、それは教科書に書かれていること・・・本当でしょうか?農産物、特に生鮮青果の日持ち向上には、全く新しい発想が必要だと思います。そして、それが減農薬となり、環境保全につながるように研究を進めたいと思います。収穫後の農産物を対象とし、新しい鮮度保持技術や加工技術を駆使することにより、農業が抱えている様々な課題(超長期保存、食の安全、食品ロス低減、農産物輸出促進、地域活性化など)解決に必要な技術開発に関する研究に取り組んでいます。
No.42
- 農学部
-

- 食料生産環境学科
食産業システム学コース 
- 農産物流通科学研究室
- 准教授
- 折笠貴寛
- おりかさたかひろ
- シーズのポイント
- 青果物・食品の加工操作を中心としたシステムの改善や最適システム
- シーズ概要
-
農産食品プロセス工学の知識を活かし、その農産物の最適な加工法を探索するとともに、それを長期間保存させ、安全でおいしい農作品を提供できるよう研究を進めています。また、研究成果を現場に応用できるよう、「実学」を意識した研究を行っています。
- 【主な研究テーマ】
-
- 遠赤外線による規格外野菜の有効利用
- マイクロ波を用いた新しい食品加工技術の開発
- 農業の6次産業化への応用
No.43
- 農学部
-

- 食料生産環境学科
水産システム学コース 
- 水産システム学研究室
(水産食品加工学)
- 教授
- 袁春紅
- ゆぇんちゅんほん
- シーズのポイント
- 魚介類の鮮度維持、高品質化の技術開発研究
- シーズ概要
-
魚介類の鮮度維持、高品質化の技術開発研究
No.44
- 理工学部
-

- システム創成工学科
電気電子通信コース
- 教授
- 髙木浩一
- たかきこういち
- シーズのポイント
- プラズマを生成するための電源(パルスパワー)技術や、環境保全、農業・食品、材料分野への応用研究
- シーズ概要
-
放電プラズマや高電圧工学は電子デバイスやエネルギー変換など、ユビキタス社会や低環境負荷社会の構築に大きく貢献している。近年は医療、バイオ、農業分野や環境保全など、新しい応用分野が広がっており、私たちは、各応用に適したプラズマを生成するための電源(パルスパワー)技術や、環境保全、農業・食品、材料分野への応用研究をおこなっている。また、明日の地球と地域と人づくりのため、小学校や科学館と連携したエネルギー環境学習にも取り組んでいる。