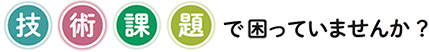教員別一覧
No.45
- 理工学部
-

- システム創成工学科
電気電子通信コース
- 准教授
- 髙橋克幸
- たかはしかつゆき
- シーズのポイント
- 水中で放電プラズマを発生させ、難分解性有機化合物を、選択制無く高速で分解処理
- シーズ概要
-
高電圧を用い、「水中で放電プラズマを発生させると、ヒドロキシラジカルなどの非常に酸化力が高い化学的活性種が生成されます。これを利用することによって、従来の汚水処理技術では分解が困難であった難分解性有機化合物を、選択制無く高速で分解処理することができます。」この技術の確立と普及実現のため、放電現象の理解、電源によるプラズマの制御、有機化合物分解効果の実証、処理システムの検証など幅広く取り組んでいます。
No.46
- 教育学部
-

- 家政教育科
- 教授
- 天木桂子
- あまきけいこ
- シーズのポイント
- 洗浄機構に関わる流体力について、界面活性剤水溶液のレオロジー挙動の解明、天然染料の各種繊維に対する染着性
- シーズ概要
-
快適な衣生活を営むための要因をさまざまな角度から研究しており、特に、洗浄と染色を大きなテーマとしています。洗浄は、いろいろな物質に付着している汚れの除去を目的とし、特に物理的要因の一つである洗浄液の持つ流体力学的作用を測定しながら、洗浄に流れを積極的に活用する手がかりを探っています。また、染色は自然界の動植物から得られる天然染料を抽出し、さまざまな繊維への効果的な染色方法を検証しています。
洗浄、染色ともめざしているのは「低環境負荷と高効率」で、近年はさまざまな機能水(電解水、ファインバブル水)の利用を積極的に研究しています。
No.47
- 理工学部
-

- システム創成工学科
社会基盤・環境コース
- 教授
- 伊藤歩
- (いとうあゆみ)
- シーズのポイント
- 水質や水の浄化、更には水域の生態系保全や廃棄物の有効利用
- シーズ概要
-
私達が使用した水は汚水となり、処理場で浄化されますが、汚れ成分の多くは汚泥という形で残ります。この汚泥は、有機物やリンなどの有用物質を含んでおり、エネルギー源や肥料原料として利用できます。しかし、汚水に由来する重金属や有機化学物質などの微量汚染物質も同時に含まれています。そこで、微生物や酸化剤あるいは光触媒の機能を利用した汚染物質除去や有用物質回収のための新しい技術の開発にチャレンジしています。
No.49
- 農学部
-

- 食料生産環境学科
農村地域デザイン学コース 
- 水環境工学研究室
- 准教授
- 濱上邦彦
- はまがみくにひこ
- シーズのポイント
- 河川や貯水池などの農業用水利施設における流動および水質の挙動に関する研究
- シーズ概要
-
水河川や貯水池といった農業水利に関わる様々な水環境について、健全で持続可能な水環境の保全を目的に、物質輸送を含めた水理実験、水環境中での藻類動態とその要因分析、低次生態系モデル等を用いた水質変動予測、底泥分析などを用いて研究を行っています。物理学的、化学的、および生物学的見地から、主に、現地観測、水理実験および数値シミュレーションを駆使して種々の水理・水質現象の解明を行っています。
No.50
- 農学部
-

- 食料生産環境学科
農村地域デザイン学コース 
- 施設機能工学研究室
- 准教授
- 山本清仁
- やまもときよひと
- シーズのポイント
- 経済的な食料生産のために、ダムや水路等の農業水理施設の寿命を延ばす方法
- シーズ概要
-
食料を生産するためには田畑に安定して水を供給することが必要です。そのために、日本全国にダムやため池、水路などの農業水利施設が建設されてきましたが、建設費用が膨大であるのも事実です。経済的な農業生産のためには、今ある農業水利施設をできるだけ長い間大切に使い、その機能を最大限に発揮させる必要があります。そのことを踏まえて本研究室では、「経済的な食料生産のための水利施設の長寿命化」について研究しています。
No.51
- 農学部
-

- 食料生産環境学科
食産業システム学コース 
- 植物環境制御学研究室
- 准教授
- 松嶋卯月
- まつしまうづき
- シーズのポイント
- 植物の生育と水管理に関連する生体計測法や栽培技術開発を中心に研究
- シーズ概要
-
温暖化や気候変動に適応できる農業技術の確立や、地域の資源を活かした高品質・高付加価値の農作物栽培システムの実現を目指しています。そのために、温度や水分条件が植物に及ぼす作用の解明や、植物の環境応答を計測・制御する技術を研究しています。植物の生育と水管理に関連する生体計測法や栽培技術開発を中心に研究を行っています。
-
- 農業の水問題へ栽培技術開発・生体計測でアプローチしています。
- 主に土壌-植物-大気間の水移動を研究しています。目的は植物水分生理の解明、灌漑効率の向上、新栽培技術の開発です。
- もみ殻培地がもつ根腐れの発生しにくい特徴について、根系の発達、培地と根の間の水移動の関係などを通じてメカニズムの解明を行い、最適な灌水法について調査しています。
- 水の流れを観察するために、中性子、近赤外線、可視光線などを用いた可視化装置の研究開発を行っています。
-
No.52
- 理工学部
-

- システム創成工学科
社会基盤・環境コース
- 准教授
- 石川奈緒
- いしかわなお
- シーズのポイント
- 土壌・水環境中での様々な物質の挙動に関する研究
- シーズ概要
-
水の汚染は土壌の、土壌の汚染は水の汚染につながり、さらにそこに生息している植物や生物に影響を与えます。
本研究では、主に土壌や水環境中での様々な元素や放射性物質、有機化合物などの有害物質の挙動を明らかにし、環境保全に役立てます。
No.53
- 理工学部
-

- システム創成工学科
社会基盤・環境コース
- 助教
- 晴山渉
- はれやまわたる
- シーズのポイント
- 太陽光や廃棄物を有効利用した汚染浄化法の開発
- シーズ概要
-
地下水・土壌汚染は、全国各地で現在も新たに発見されています。地下水・土壌汚染の浄化手法は、既に存在しますが、その低コスト化と環境負荷の低減化が望まれています。そこで、太陽光や微生物といった自然の力を利用した、廃棄物を環境浄化剤として有効利用した汚染浄化法の開発を行っています。また、上記手法を難分解性の有機化合物含有廃水の処理に応用する研究にも取り組んでいます。