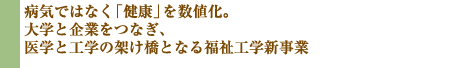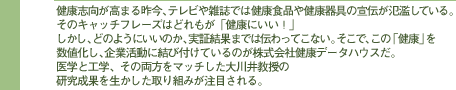|
|
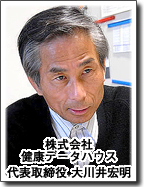 |
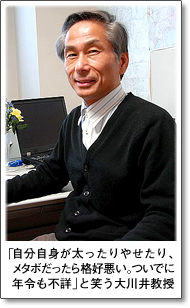 「健康データハウスは文字通り健康データの調査をしている会社です。わかりやすいと思いますよ」。大川井教授が言うとおり、健康は誰しも身近なことで関心が高い。しかし、健康に関わる範囲は実に広い。いわく、「例えば、住居環境の調査でも、間取り、ベッド、ふとん、カーテンの色から材質までいろいろある。そういうモノから生活習慣まで全般にわたる調査が必要です。テレビなどでは"健康にいい"とか"寝心地がいい"とかどんどんコマーシャルを流しているけど、本当にそうなのか?一般の方々は納得して使っているのか?産業側もデータを作りにくいのではないか」
「健康データハウスは文字通り健康データの調査をしている会社です。わかりやすいと思いますよ」。大川井教授が言うとおり、健康は誰しも身近なことで関心が高い。しかし、健康に関わる範囲は実に広い。いわく、「例えば、住居環境の調査でも、間取り、ベッド、ふとん、カーテンの色から材質までいろいろある。そういうモノから生活習慣まで全般にわたる調査が必要です。テレビなどでは"健康にいい"とか"寝心地がいい"とかどんどんコマーシャルを流しているけど、本当にそうなのか?一般の方々は納得して使っているのか?産業側もデータを作りにくいのではないか」
十分正確なデータがない現在、健康食品や健康グッズの販売でもイメージ的な宣伝だけが飛びかっている。そこできちんとデータを集めて健康を定量化し、数値で表す研究を始めたのが大川井教授である。この実験データに対し、住宅関係から食品関係、スポーツ、レクリエーションなど広い分野にわたって着目する企業は多いという。欲しいという企業にはデータを提供しており、人々の健康を願うこのような真摯な姿勢を持つ企業とよくタイアップして研究と事業を発展させたいともいう。
大川井教授は、もともとはエンジニアだった。大学卒業後に勤めた会社では工学の知識で医療機器を作っていたが、医学がわからないとできないことが多いのに気づき、医学博士の学位を取得する。その後、再び工学の門を叩いて工学博士の学位を取った。医学と工学の両方の立場を取り入れて健康を研究するに至った大川井教授だが、「医学と工学の間にはギャップがある」という。
「お互いに自分の世界の外を新たに勉強することは大変なんですね。医療界は役に立つものが欲しいが、技術の詳細はわからない。それをつくる企業は医療の世界のことはわからないままに、工学技術優先でつくってしまう。このような中でも「医工学」としてギャップは埋まってきたが、新たに「健康」というテーマが大きくなった。これは医学でも工学でもカバーしきれない。あっ、これが福祉工学かと気がついた。そこで、医学と工学の分野のギャップをつなぐ掛け橋、企業と大学の取り組み姿勢のギャップをつなぐ掛け橋になりたい。その手段が福祉工学技術、すなわち証拠を見せることのできるデータなんです」
健康データの調査は大学の研究とほぼ一体になっている。大学は原理優先という中で、企業はなるべく早く結果を出して形にすることを求められる。厳しいけれども会社を設立した限り、結果を得られるものを選んでデータを出していく。そのこと自体が大学の研究の効率アップにつながり、起業したメリットなっているという。
「よく大学の先生は、企業の苦労を知らないといわれますが、結果を出すことの大事さと難しさはわかります。しかし、企業は結果を急ぐ余り、モノやサービスを提供する本当の使命を見失ってしまうこともある。原理を大事にする大学は、失敗したらそれを糧に本質に迫る研究を重ねていく。生温いと思われるかもしれないが、そこに重要な使命があるのです。両者とも一長一短があり、私は両方のいいところを出していくと、企業の方に理解を求めたいですね」
 平成19年4月、研究の拠点となる「健康見守り実験ハウス」が、岩手大学工学部の一角に完成した。この家では、屋内に各種センサーを仕掛けて、被験者がごく普通の生活を送っているときの健康や体調に関するデータをとる実験が行われている。部屋の広さ、建材の種類、色、換気、温度、湿度、明るさなど部屋の環境を変えることで、例えば睡眠にどんな影響があるのか。それを数値化していくのである。
平成19年4月、研究の拠点となる「健康見守り実験ハウス」が、岩手大学工学部の一角に完成した。この家では、屋内に各種センサーを仕掛けて、被験者がごく普通の生活を送っているときの健康や体調に関するデータをとる実験が行われている。部屋の広さ、建材の種類、色、換気、温度、湿度、明るさなど部屋の環境を変えることで、例えば睡眠にどんな影響があるのか。それを数値化していくのである。
こうした実験の結果が出れば、例えば「快適な住まい」など、住宅についての漠然とした評価や宣伝文句が、イメージではなく数値を通してより具体的に知る手がかりになるし、住まいや健康グッズなどの産業面でも説得力を高め、消費者は納得して購入するようになるだろう。
 大川井教授は、「自分の視点を変えることができたし、考え方がより明確になった。研究を効率よく進めることも利点です」と起業のメリットを挙げる。
大川井教授は、「自分の視点を変えることができたし、考え方がより明確になった。研究を効率よく進めることも利点です」と起業のメリットを挙げる。
その上で、大学の研究活動を加速するとともに、社会にデータを提供する企業活動をうまく機能させたい。併せて、研究活動を続ける大学院生の職場にもしていきたいと、目標を掲げる。
おおかわい・ひろあき
|
||||||||||||||||||||
株式会社健康データハウス
|
||||||||||||||||||||