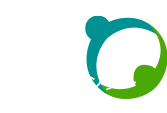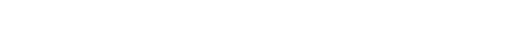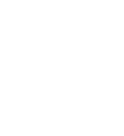地域課題解決プログラム(久慈市)の現地調査を行いました
平成29年6月23日から24日にかけ、人文社会科学部の杭田俊之准教授とゼミ生2名が、地域課題解決プログラム「珍品水産物活用で、個性あふれる肴場放浪によるまちづくり」の現地活動を開始し、第1回は久慈市の水産物の流通等に関する現地調査を行いました。
地域課題解決プログラムとは、学生の積極的な地域社会への参画を促すとともに、地域社会が抱える様々な課題を指導教官の下、斬新な学生の視点から研究を行い、産学官連携による取組として、また岩手大学の地域貢献活動を実践する取組として平成18年度から継続している事業です。本件の活動は久慈市を舞台に平成29年度から新たに取り組むもので、久慈市産業経済部林業水産課、当機構(久慈市共同研究員、久慈エクステンションセンター)が学生とともに連携して活動を推進しております。
活動第1回目となる今回の調査では、久慈港で水揚げされる水産物の流通状況・経路を確認するとともに、地域資源・未利用資源を発掘するべく、(株)マルサ嵯峨商店、久慈市漁業協同組合、(有)北三陸天然市場から会社概要や主要取扱い魚種・商品等に関する説明を受け、施設見学をさせていただいくとともに、地魚を提供している市内飲食店にて仕入れ状況等に関するヒアリングや意見交換を実施しました。特に鮮魚・加工商品販売及び飲食事業にて一般消費者との取引を行う(有)北三陸天然市場からは、地元水産資源活用や地魚の流通事情に関する課題と期待双方の情報を得ることができ、また魚種開拓やメニュー開発に関する相談・協力をいただけることとなりました。
視察先の方々のお話から、久慈市を含む三陸沿岸の水産物のうち、特に鮮魚関連の流通については、漁獲時期に多少の誤差はあるものの、首都圏等に出荷される鮮魚のほとんどが同一の魚種であることがうかがえました。また、久慈市漁業協同組合が運営する魚市場からの流通状況から、魚市場に水揚げされる以前の漁業従事者からの情報収集も有用であることが考えられます。
今年度の活動は始まったばかりですが、地域資源・未利用資源を発掘するには更に調査を重ねる必要があり、流通状況を改めて整理して俯瞰的に状況を把握することも必要です。また、様々な漁業・水産関係者と交流する中で久慈市の地魚・水産特産物を見出し、産学官民が連携した活動として本プログラムを展開すべく、今後も引き続き調査を続けて参ります。