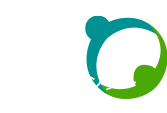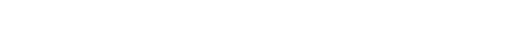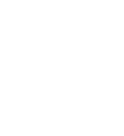公開講座「地域政策入門-生活と経済・環境」を開催しました
講座名:地域政策入門-生活と経済・環境
実施日:平成30年7月28日(土)
受講者数:50名 定員数:50名
【目的】
高校生を主な対象として,人文社会科学部地域政策課程の教育内容及び人材養成像を紹介するだけでなく,地域の現状を理解し課題に取り組むうえで,地域政策に収斂する法学・経済・環境学の視点が不可欠であることを十分に理解してもらうことを目的とした。
【活動実績】
2018(平成30)年7月28日(土)13:30~16:20,附属図書館生涯学習・多目的学習室において,「地域政策入門-生活と経済・環境」をテーマとして,法学・経済学・環境学の3分野から話題を提供した。
最初に藤本幸二准教授が「政策とは何か,政策と法・経済・環境との関わりとは-地域政策について学ぶ前に-」を題目に講演を行った。まず政策の基本的内容から始め,政策の立案と評価の詳細に触れ,次に政策と法・経済・環境との関わりについて,政策は法により制度となるべきこと,経済は政策の目標ともなり,かつ評価指標でもあること,また環境は公共政策の典型であることなど具体的に解説した。
次に佐藤一光准教授が「地域経済と生活のリアル」と題して講義を行った。高校生を始め若い世代にとってリアルな問題として,賃金の問題,教育・子育てにかかる費用と公的補助のあり方について日本の現状を説明し,次に「なんとなく生き辛い」という生活実感の原因を,家族に関する制度を中心に掘り下げ分析を行った。
最後に塚本准教授が「〈企業-NPO〉連携・協働による環境保全―地域も含む3者間の “Win-Win関係”へ―」の題目のもと,まず企業とNPOの連携・協働による環境保全活動が近年注目されていることと,その背景・意義を解説し,次に連携・協働が企業・NPOだけでなく,地域社会にも利点となっていることを確認した。最後に,岩手県はじめ各地での成功事例を紹介し,連携・協働の実情と課題を理解してもらう機会とした。
そして講義の後,総括として質疑応答を行った。事前に提出してもらった多数の質問だけでなく,会場からもその場で質問があり,有意義な意見交換となった。
【今後の課題】
・「質疑応答・討議」の充実・実質化が課題である。今回は意図せず比較的うまく運んだにせよ,受講者からの個別の質問に答えるだけでなく,講演者3名の間で実質的な意見交換をし,会場全体として議論を活性化するには,講座テーマの選定,講演者間の事前の打ち合わせ,共通の問題に関わる質問を募る様式への質問票の改訂など,入念な検討と準備を要する。
・募集定員を超過した場合の受け入れ方について,高校生を優先するのか否かなど要検討。さらには会場・募集定員についても再考の余地があるだろう。